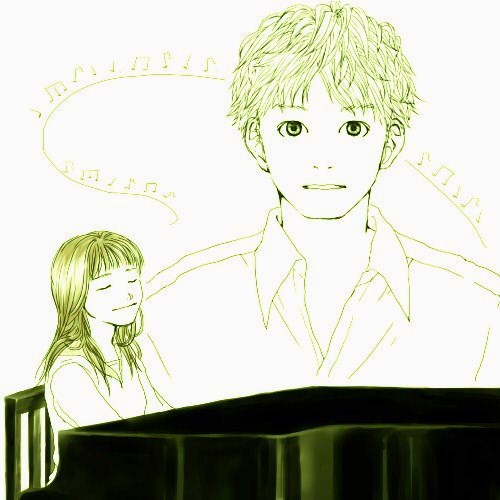
サティのジムノペディ
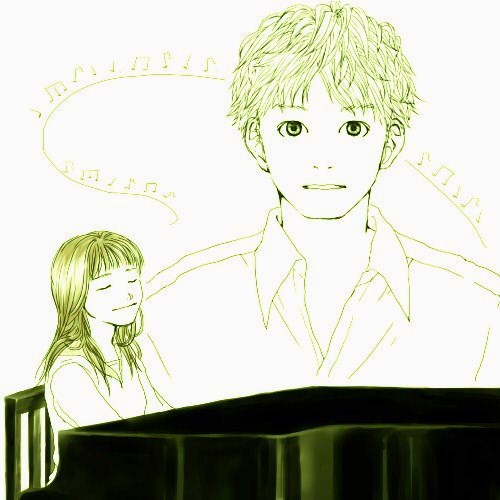
僕の通っている高校は、創立数十年にも亘る、結構伝統のある学校だ。
でも、やはり年月ってのは人も建物も変えていくもので、取り壊しや建て直しなど色々なことがあって現在のこの学校は成り立ってる。
そんな僕の通う学校の離れには、旧校舎と呼ばれるところがあるが、そこがまた木造建てでえらく古い。
創立の際にあった教室などがある校舎なので、もう誰も入らないけど、その旧校舎の中には一つの音楽室がある。
なぜかその音楽室だけは閉鎖されてなくて、気になって僕が聞いたところによると、何やらその音楽室には一つのエピソードがあった。
実はこの学校の設立の際、色々と寄付をしてくれた老人がいたのだそうだ。
まぁ、いわゆる足長おじさんという奴だろう。
その足長おじさんが多大な寄付を学校にしてくれたが、その寄付の条件が、その音楽室を作ることだったらしい。
老人は音楽が大好きで、学校に通う子供に、音楽の素晴らしさを分かってもらいたかったのだそうだ。
よくやる老人だ。まぁ、寄付という条件があるからこそのものだろうけど。
ともかくそんな経緯のあった音楽室だけど、結局のところ閉鎖はされずとも今は使われていないわけで、ただ旧校舎でポツリと佇んでる。
そこに、彼女はいたわけだ。
「ねぇ祐(ゆう)ちゃん。みんなで肝試ししない?」
友人である湖東真紀(ことう まき)がそう言ってきたのは、僕が昼食のパンを買いに行こうとしたときだった。
肩口まで伸びた、栗色の髪のもみ上げが結ばれてる童顔の女の子だ。
その隣では、親友の新田智樹(にった ともき)が、白い歯を見せたにこやかな笑顔を見せている。
「肝試し……? 別にいいけど、何で急に?」
「えと、旧校舎は知ってるでしょ? あの離れの」
真紀は指を人差し指を立てて聞いてきた。
それはもちろん知っている。あの旧校舎は伝統があるので結構有名なのだ。
「そりゃ……。で、その旧校舎がどうしたって言うのさ」
「それがさー。あの旧校舎、もうすぐ完全に取り壊されるんだってよ」
今度は智樹が真紀に代わって喋り始めた。
僕の机の上に尻を乗っけて。
「取り壊し? また急な話で……」
「もうあの旧校舎も大分傷んでるしな。底が抜けて、入った人が怪我したら危ないってんで」
「確かに、建ってからもう随分建つもんね、あの校舎。まぁ、それは分かったとして……、その旧校舎がどうしたの?」
僕はくどいかもしれないが聞いた。いや、それなりに予想はできたよ。
でも、やっぱり確信がほしかったんだよね。
「ったくもー、ここまできたなら分かるでしょ? だーかーら、その旧校舎が取り壊されるから、最後に肝試しでもそこでしようかって話になったのよ!」
真紀がプンスカと効果音でも出てきそうな怒り方で言った。
「で、まさかとは思うけど、その肝試しする日って…………」
僕はそこまでの流れで、何となく嫌な予感がして聞いた。
案の定、
「よくぞ聞いてくれた祐一っ! 俺の親友だけある! ズバリ、その日付は今日だ!」
机に尻を乗せたまま、大げさに手を振って智樹が言った。
こいつは時々人のことをまったく考えていないのではないかと錯覚する。いや、実際考えてないのだろう。
多分、ここで僕が、「用事があるから」と言ったとしても、おそらく首に縄つけて連れて行くはずだ。
「ふぅ……。分かったよ、行けばいいんでしょ。と言うか行かないとダメなんでしょ?」
まぁ、用事はないし、別にいいだろうと思う。
「わー、さすが祐ちゃん!」
それに、真紀も喜んでるし、悪い気はしない。
その時、昼休みの終わりを告げるチャイムが、教室に響く。
あ、パン買いに行くの忘れた。
と、まぁ、こんなそんなで、僕達は夜の旧校舎玄関前に来たわけだけど。
「……何でこうなんのかなぁ? 智樹」
僕は一人でろうそくを持ちながら、智樹に聞く。ちなみに、僕はラフなシャツにジーンズという簡単な格好だ。
智樹は隣に真紀を連れてろうそくを持っていた。
「仕方ないだろう。俺達は全員で三人。そして、こんな暗くて怖いところに、真紀ちゃんを一人で行かせるのは男として、いや、人としてあってはならぬ! つまり、俺と真紀ちゃんがペアとなり、お前が一人で行くという結論に至るわけだ!」
高笑いを上げて言い切る智樹。
だが、明らかに間違っている部分があるぞ。
「だっかっらっ! なんでそれで真紀がお前と行くことになるんだよ!」
真紀は真紀で事情をよく分かっておらず、愛想笑いを浮かべている。
もう少し女として危険を感じたらどうなんだろう。
この智樹は狼同然、いや、狼より性質が悪いかもしれないのに。
「フフフ……。それは、まぁ、真紀と、若さと、情熱と……」
と、智樹は言いながら、颯爽と旧校舎の中に入っていこうとする。真紀を連れて。
「ちょっとまて! 誤魔化すなぁ!」
「ま、良いじゃんか祐一。ここは俺と真紀ちゃんペア。お前は単独でってことで。じゃ、先行ってるよー」
「じゃーね、祐ちゃん。また後で会おうねぇ」
「……ったくもぉ」
僕は智樹達を追いかけようとしたけど、面倒くさくなって止めた。
まぁ、智樹も別に真紀にまでは変なことしないだろう。
「ふぅ……。じゃあ、僕も行こうかな」
智樹達が入って数分経った後、僕も旧校舎に入ることにした。
旧校舎に入ると月明かりも窓以外は遮られ、ろうそくが頼りになった。
ここに来る前に智樹からルールを聞かされたが、ゴールはここの四階にある美術室前だ。
となると、先に階段を探す必要があるんだけど……。
ギシギシと床の軋む音を鳴らしながら、僕はろうそく片手に廊下を進む。
別に怖がりではないが、このときはなぜか微妙な怖さを感じた。
やはり、夜の学校だからだろうか。
「あ、あれ、階段……?」
目の前の角に見えたのは、少し凹凸のある影。
その角に行ってみると、思ったとおり、古びた階段があった。
「うへぇ……。大丈夫かなぁ?」
まるで虫の食った紙のように、穴ぼこだらけの階段。
これで落ちたら一溜まりもない。特に三階、四階と上がっていけば、その危険度は育毛促進剤の毛が生える確率をも超えるだろう。
まぁ、一応それでも先に行った智樹達は上れたのだろうと思うし、多分、大丈夫だ。
僕は階段を恐れながらに上って、今度は二階の廊下を進む。
そういえば、この階には色々な旧部室もあったな。
確か、文芸部とか、科学部とか。何かそんな感じの文化系だったはずだ。いやまぁ、そもそも運動系は校舎に部室なんてあまりないけどね。
そんなこんなを考えて夜の不気味さを忘れていると、何か、音が聞こえたような気がした。
「ピアノ……?」
まさか、そんなはずない。
この校舎には智樹と僕と真紀しかいないはずだし、あの二人がピアノなど弾けはしない。
それに仮に弾けたとしても、肝試しの途中でそんなことするはずがないじゃないか。
しかし、微かに聞こえるそのピアノの音は、止むことなく華麗な音色を僕の耳まで届けてきた。
ちょっと悲しそうな、美しい曲。
あまり音楽について詳しくない僕でも、それが上手であることは分かった。
そして、僕はそれに釣られるようにその音色のする場所を探し始めていた。
夜中に流れるピアノの不自然さもあったが、僕は何より、この音楽を奏でる人が誰なのかを見たかった。
音楽室は二階にあるので、少し探せばすぐに見つかった。
近づくにつれて大きくなる音色。
他の教室は閉鎖されているが、この教室だけは開いている。もちろん、ピアノがここから聞こえてくるのは間違いない。
僕は恐る恐る音楽室の戸に手をかけて、少しだけ開けた。
なんだか、もし見つかったら怒られそうな気がしたし、演奏している様子が見たかったから。
音楽室の中は月の薄明かりが照らしていて、覗いた戸の向こうには、一人の少女がいた。
ピアノの前に座って、目を瞑って演奏している。きっともう感覚で覚えているのだろう。
長い黒髪のロングヘアーが、まるで流水のように煌びやかだ。
そして、服はどうしてか分からないが、セーラー服を着ている。最初はうちの学校の制服かとも思ったが、うちはあんなセーラー服ではない。
どこか別の学校の生徒なのだろうか。
それにしてもいちいちこんな旧校舎に忍び込んで、使われてない音楽室のピアノを弾くなんて、物好きだ。
よっぽどここのピアノが好きなのだろうか。
そんなことを僕は考えていたら、つい誤って扉に足をぶつけてしまった。
――まずい……!?
と、思ったけどもう遅い。
少女はそのぶつかった音に気づくと、はっと目を向けて扉を見た。
「誰……?」
一瞬、出て行くことを躊躇ったが、戸の隙間から僕のことは見えてるだろうし、逃げるなんて格好悪いと、僕は思った。
だから、少ししどろもどろだけど、素直に出て行くことにした。
「えと、あの、……べ、別に、怪しい者じゃなくて、ホンと。えっと、ピアノの音が流れてきたから、ちょっと気になって……」
僕が必死に弁解している間、少女は呆然と僕を見ていた。
そして、
「私が…………見えるの?」
僕に聞いてくる。
「い、いや、それは、もちろん」
「本当に……?」
「うん……」
そのとき、僕は何で少女がそんなことを聞くのか、理解できなかった。
「じゃあ、君はいつもここでピアノを弾いてるんだ?」
「うん」
僕が聞くと、少女――伊代(いよ)はそう答えた。
話を聞いたところによると、伊代は十数年前からそうらしい。つまり、幽霊なのだ。
僕はこれでもUFOとかネッシーとかは信じるほうだし、オカルトも案外信じてる。
だから、彼女の言うことに少々の疑いはあれど、何とか受け入れることができた。
ちなみに、僕はいまピアノの前で座る伊代の横で、そのピアノにもたれかかってる。
「何か、幽霊って言うと透けてるとか怖いとかのイメージがあるけど、別段普通の人間と変わらないんだね」
「分からない……。私、ここから出れないし、他の幽霊知らないから」
「あ……、そっか」
考えてみればそうだ。
この子は自縛霊みたいなものなのだから、他の幽霊なんかに会ったことはないのだ。むぅ、失言だった。
そういえば、僕が部屋に入るまで彼女の弾いていた曲は、一体なんと言う曲なのだろう。
何となく気になった。
「ねぇ、君が弾いてた曲さ。なんて言う曲なの?」
「あれは……、サティって作曲家の曲なの。曲名は、ジムノペディ」
音楽がとても好きなのだろう。
そう言って僕に話すときの伊代は、笑顔だった。
だからかもしれない。
僕はまた、その曲が聴きたくなった。
「もう一度、さ。弾いてくれないかな?」
「でも……、私、下手でしょう?」
「そ、そんなことないって! とても上手かったよ……。少なくとも、僕はそう思った」
僕がそう言うと、伊代はまたあの笑顔をする。
眩しいくらいに、綺麗な微笑みを。
そして小さく「嬉しい……」と呟く。
伊代がそう言うと、なぜか僕も嬉しくなった。
僕の頼みに応えるように、月明かりが差す中、伊代は鍵盤に手をかける。
演奏が始まると、伊代の目は自然に瞑られ、綺麗な音色が流れる。
――サティの、ジムノペディ……。
彼女の言っていた曲名を、僕は自然と頭の中で繰り返していた。
そして、こんなことを考える。
彼女は、いつもここで一人ぼっちだったのだろうか。
たった一人で、誰も聴かないクラシック曲を、演奏していたのだろうか。
そう思うと、なぜか僕は、悲しくなった。
同情かもしれない。あるいは、悲観。
伊代の弾くサティのジムノペディが、まるで泣いているように感じた。
それは、曲の雰囲気でもあったけど、僕には違うところにもあるような気がした。
曲も、もう終わる。
伊代は消えていく光のように、演奏を締めた。
「どう、かな……?」
少し恥ずかしそうに、伊代は僕に尋ねてきた。
「うん。やっぱり、上手いよ」
僕は向き合いながら、笑って伊代に答えた。
そのとき、誰かの声が廊下のほうから聞こえてきた。
「おーい、祐一! どこいるんだー!」
「祐ちゃーんっ!」
僕は、その声ですぐに真紀と智樹だと分かった。
どうやら僕を探しにきたらしい。
考えてみれば、僕は肝試しをやっていたのだった。ついついここで長居してしまった。
「おーい! 僕はこっち!」
そう叫んだら、ギシギシと廊下を進んで、智樹と真紀が音楽室に入ってきた。
「なんだよ、そこにいたのか。美術室でずっと待ってもこねぇしよぉ。てっきり、本物のお化けに会って気絶してんのかと思ったぜ」
憎たらしい笑みを、ニタニタ浮かべながら智樹は言う。
まぁ、幽霊にはあったけどな。確かに。
「祐ちゃーん! 大丈夫だったぁ?」
智樹の言うことを信じてるのか、真紀は本当に心配そうだ。
我ながら、こういうのを見ると本当、救われるよな。智樹は余計だけど。
さて、じゃあ二人に伊代を紹介しないとな……。
そう僕が思って、二人からピアノのほうに向き直ると、
「……あれ?」
伊代の姿は、まるで初めからそこにいなかったように、跡形もなく消えていた。
僕が肝試しの翌日、伊代に会いに行って気づいたことだけど、どうやら伊代の姿は僕にしか見えないらしい。
しかも僕が見える場合も、伊代と二人でいるときだけなのだ。
他人がいると伊代の姿は消えてしまう。
なんで僕だけが伊代の姿を見ることができるのかは分からない。
それはともかく、僕はあの肝試しの後から、放課後に伊代と会うことが日課となっていた。
と言っても、まだあれから三日しか経っていないんだけど。
「伊代って、何十年もここにいるんだよね。何か理由でもあるの?」
今日も今日とて、僕は音楽室のピアノにもたれかかってる。
その側には、ピアノの前で椅子に座る伊代がいる。
「よく分からないの……。亡くなって随分経つし、もううろ覚えだよ」
「うろ覚えってことは、少しは覚えてるんでしょ?」
「うん……。本当に少しだけど」
僕は伊代のことはピアノを上手に弾けて、音楽が好きってことぐらいしか知らない。
だからか、何となく伊代のことを聞いてみたくなったのだ。
「どんなのか、教えてよ」
「良いけど、つまらないよ」
「別に良いって」
空に浮かぶ夕暮れが、音楽室を照らしている。
伊代と僕の影が、ピアノや床に重なり合っていて、少し綺麗なもんだなぁと感じた。
伊代は少し躊躇いを見せていたけど、話す気になったらしい。
僕のほうじゃなくて、ピアノを見ながら話し始めた。
「亡くなる前の、学生だった頃、ある男の子がいたの。……もうその人の顔も、憶えてないけどね。
その人はいつも私のピアノを聴いてくれてたの。上手いよって、綺麗だよって。うん……、そう言ってたの。
私は、そんなその人の一つ一つの言葉が大好きで、その人のことが、誰よりも愛しくて……。
だから、その人に告白するつもりで、たった二人の演奏会を開こうとしたの。その人は観客で、私は、ピアノの演奏者。
でも、その前に私は死んじゃった……。ただの交通事故で、呆気ないくらいに」
伊代は、ただ言葉を紡いでいく。僕の横で。
その目には、何が映っているんだろう。
愛していた人の顔も忘れ、曖昧な記憶の闇で縛られたまま、伊代はこの音楽室で弾き続けていたのだ。
叶うことのない演奏会を。
叶うはずのない演奏会を。
「……馬鹿だよね、本当。死んだ後になっても、憶えてもいない人を、待ち続けてるなんて……」
伊代の目には、透き通った涙が浮かんでる。
背中から差し込んでる夕暮れが、その涙を影で染める。
「……馬鹿じゃないよ。…………馬鹿じゃない」
僕には、そう言って伊代に胸を貸してやることしか出来なかった。
嫌なことを思い出させて、妙な罪悪感もあったけど、僕はこのとき、初めて伊代を知った気がした。
「ねぇ、祐ちゃん。最近、いっつも放課後になにしてるの?」
授業も終わり、帰りの準備をしていた僕に、真紀はそう聞いてきた。
「んー、何と言われても……」
まさか幽霊と一緒にいるとは言えるはずもない。
言ったところで、普通見えない人は信じないし、悪ければ僕が精神患者扱いされかねない。
「おいおい。まさか、なーんか変なことやってるんじゃないよねぇ祐一くーん」
見事なまでに憎らしい笑みを、真紀の側で智樹はしている。
「別に、そんな変なことはしてないよ。少なくとも、智樹が想像してるようなことはね」
「じゃあ何してんだよぉ。親友なんだから、教えてくれたっていいじゃんか」
「強いて言えば……、演奏会、かな」
「演奏会?」
「そ、演奏会」
智樹は訝しげな顔をしているが、実際、演奏会と言ってもおかしくない。
だって、演奏者の曲を聴いてるんだから。
「えー、いーなぁー祐ちゃん。私も演奏会行きたいぃ」
真紀は僕の言うことを真に受けて羨ましそうにしてる。
その様子を見てると、つい笑ってしまいそうになった。
――演奏会、か。
自分で言ったことだけど、なんだかその言葉にちょっとした悦を感じてしまった。
「……演奏会?」
「そう。ここで、いまやってみてくれないかな」
僕の言葉に、伊代は目を見開いて呆然とした顔を見せる。
「どうしたの急に? それに、いつも曲は聴いてるのに……」
「そういうのじゃなくてさ。僕が観客になって、伊代が演奏者。そんな感じのだよ」
僕はそう言いながら、適当に置いてあった椅子を、部屋の中央に持ってきた。
それは、観客席で、僕はそこに座る。
「じゃ、お願いします。演奏者さん」
僕がそう言うと、伊代はちょっと恥ずかしそうにした。
でも、一応は演奏する気になったみたいだ。
「ではこれより、柊(ひいらぎ)伊代による、ピアノ独奏、サティのジムノペディを演奏いたします」
立ち上がり、そう言って一礼する伊代。
僕は、このとき初めて、伊代の苗字を知った。
そういえば、ずっと名前で呼んでいた気がする。
伊代は座って、静かに呼吸をする。
鍵盤の上に手を置いて、目を瞑るのが、僕には本物の演奏者に見えた。
そして、曲は流れる。
あの少し悲しそうで、美しい音色が、僕の耳の中に入ってくる。
でも、最初に出会ったときと違って、泣いているようには感じなかった。
いまは、曲も笑っているような感じがする。
僕と伊代の演奏会。
たった二人の世界が止まっているように、伊代はサティのジムノペディを奏でる。
僕は伊代の好きだった人でもないし、まして過去の人間でもないけど、少しは、伊代に何かしてあげられたのだろうか。
あのとき果たせなかった約束を、こうして僕が聴くのは、やっぱり反則なのかな。
「ねぇ……」
「……ん?」
伊代が演奏の途中だけど、目を開けて声をかけてきた。
その手は、まだ鍵盤の上を動いている。
「……あの人も、もし演奏会があれば、あなたみたいに聴いてくれたのかな?」
伊代の声は、少し寂しそうだった。
僕は何を言えば良いのか、少し迷った。
きっと何か良い言葉をかけてあげたほうが良いんだろうけど、結局僕は、ただ自分の思ったことを言った。
「……僕には分からないよ。でも、それは伊代が一番分かってるんじゃない?」
僕の言葉を聞くと、伊代はまた静かに目を瞑った。
その顔は、少し微笑んでいた。
たった二人の空間で、サティのジムノペディは流れている。
それは傍から見れば寂しい演奏会かもしれなかったけど、少なくとも僕にとって、この演奏会は最高だった。
演奏は終わりを迎える。
こうして、僕らの演奏会は終わった。
最後に、僕は伊代の照れくさそうな顔を見ながら、拍手を送った。
次の日学校に来てみて、旧校舎の取り壊しがバタバタと始まっていたことには、驚いた。
もうすぐ取り壊されるとは聞いていたけど、それでもやっぱり実際にその様子を見ると、ちょっと寂しく感じた。
そしてその後聞いたことだが、何でも昔この学校に多大な寄付をして、しかもあの音楽室を建てさせた老人の名は、柊(ひいらぎ)と言ったらしい。
まぁ、偶然同じ苗字ってのもあるしれないけど、僕は何となくこれが伊代の先祖とかに当たるんじゃないかな、などと思う。
老人が音楽好きでその祖先も音楽が好きってのも、皮肉なもんだけど、このときの僕はその老人にちょっとだけ感謝をした。
もし伊代が音楽が好きじゃなかったら、僕は伊代と会ってなかったかもしれないしね。
ともかく、そんなちょっとした縁みたいなものがあって、伊代は音楽室にいたわけだけど、結局伊代の好きだった人は、誰なのだろう。
――と、そんなことを取り壊しの終わった旧校舎の上で考えたりしていた。
風が少し吹いて寒い。
伊代の姿はもうどこにもなく、ただそこには壊されたピアノが置いてある。
「よぉ祐一。何してんだ? こんなところで」
智樹がこっちに来ながらそんなことを聞いてきた。
「んー、もしかしたら、いるかもしれないと思って」
「何が?」
「幽霊」
「……そですか。ところで、演奏会どうだった? 良い演奏だったのか?」
「そうだね。もう二度とないけど」
「二度とない……? そりゃ残念だな。たった一度っきりの幻か」
智樹はあの肝試しをした日から、何となく僕が旧校舎に行ってるのを知ってたんじゃないか。
そう思った。やっぱり、親友だけあるからかな。
僕と智樹は、瓦礫に座り込んだ。
「祐ちゃーん! 智樹くーん!」
真紀が走ってこっちに来るのが分かる。
「すっごいの! 何か噂になってるよ!」
そして肩で息をしながら焦った剣幕で話し出す。
ちょっと落ち着いてくれ。
「……何がそんなにすごいの?」
僕が聞くと、真紀はよく聞いてくれましたとばかりに、胸を張った。
「実はね、昨日の夜、この旧校舎から、幽霊が出たの!」
「……幽霊?」
智樹がオウム返しで聞く。
「そう! 何かね、昨日の夜、夜中に目が覚めたから、ちょっとそこのコンビニまで飲み物を買いに行こうとした生徒がいたらしいの。でね、その生徒が、学校の前を通り過ぎるとき、何となく旧校舎を見たら……、長髪の女の子の幽霊が、ボゥ……と出てきたらしいのー! しかもその幽霊、新校舎の音楽部室に入って行ったんだって!」
大げさに身振り素振りを付けながら、真紀は僕と智樹に捲くし立てる。
僕は何となく予感はしたけど、やっぱり一応尋ねてみることにした。
「ねぇ、その幽霊って、うちの昔のセーラー服着てて、黒髪じゃない?」
「……な、何で知ってるのっ! 祐ちゃん」
真紀が驚くのを尻目に、僕はすぐに立ち上がった。
「どこ行くんだ? 祐一」
智樹も立ち上がって、聞いてくる。
「幽霊に会いに……、かな」
「演奏会か?」
ニタニタと笑いながら、智樹はついて来る。
やっぱり、憎たらしい奴だ。
「え、え、どういうこと、祐ちゃん」
慌てて真紀は追いかけてきて、僕に聞いた。
うーん、なんて言えばいいのかな。
あー、そうだ。
「サティのジムノペディが、待ってるんだ」
Copyright(c) 2012
yano yu-zi All rights reserved.